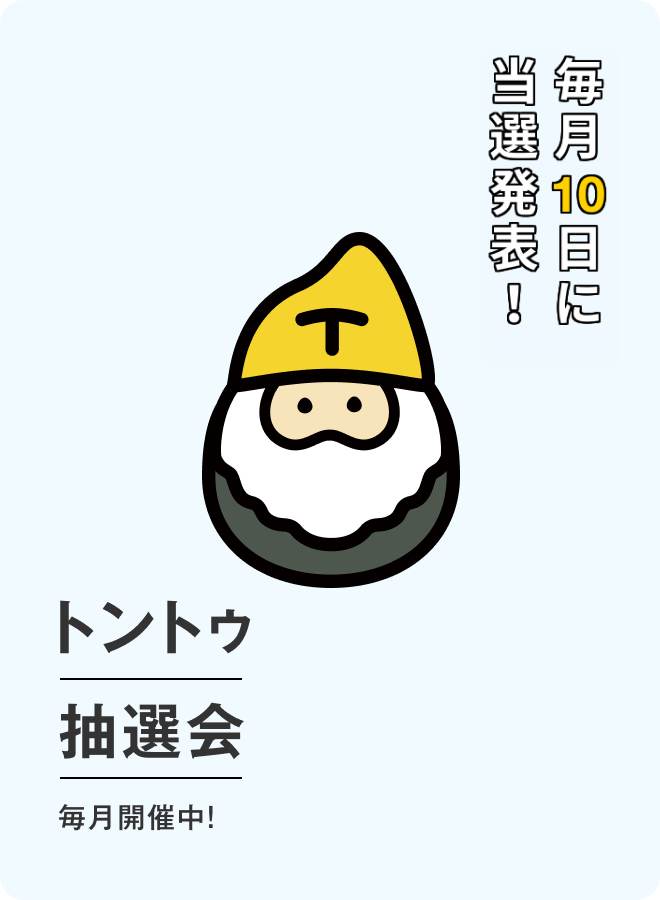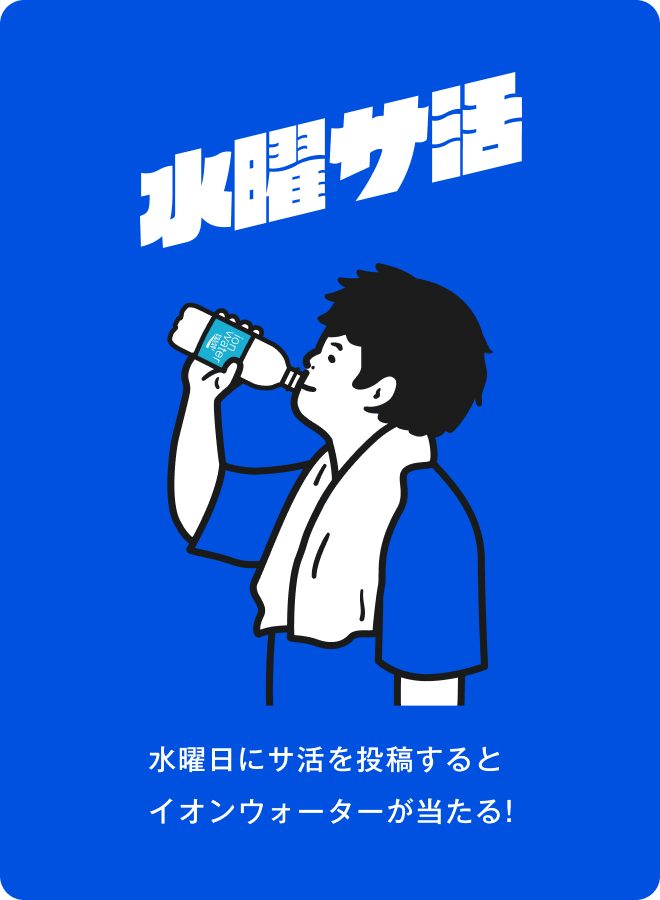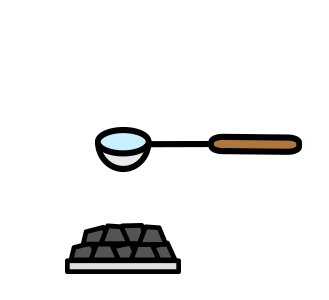サウナ×パエリア×和庭園で熱を味わう 組紐KOBE(兵庫県神戸市)サウナ誕蒸#12
サウナ大好きクリエイティブディレクターの相沢あいさんによるインタビュー連載。サウナを作った方の想いやこだわりなどを深掘りしていきます。
サウナ施設を立ち上げた方へのインタビュー連載「サウナ誕蒸」。今回は神戸市営地下鉄西神・山手線、西神中央駅から車で約10分に位置する組紐KOBE。

日本庭園の巨匠が手掛けた和庭園と築120年の古民家がサウナ施設として生まれ変わり、パエリアの世界大会出場経験のある腕前を持つオーナーが振る舞うパエリアや本格的なアメリカンバーベキューを楽しめて宿泊もできる施設です。
一見、バラバラとも思える文化がなぜそこで融合しているのか。ミクスチャーカルチャーに込められた想いとは。オーナーの植月孝明さんにお話を伺いました。

植月孝明
組紐KOBE代表
20年間サラリーマンとして営業職に従事。趣味のアメリカンバーベキューからパエリアへと関心を深め、パエリア世界チャンピオン「anocado restaurante+」結城優氏に師事し、世界大会にも挑戦。テントサウナ体験を契機に、サウナの魅力に開眼。2024年3月、貸切古民家サウナ組紐KOBEをオープン。
分かち合う文化が導いたサウナとの出会い
── サウナを好きになったきっかけを教えてください。
紐解くと、15年ほど前にアメリカンバーベキューに夢中になったのが始まりでした。大きな肉を焼いてみんなで分け合うスタイルに惹かれ、硬い肩肉をどう美味しく食べるかという工夫の中に、黒人文化の知恵や分かち合う温かさを感じたんです。
その延長でパエリアにも興味を持ち、パエリア世界チャンピオンで師匠の結城優さんから「本来のパエリアは海鮮料理ではなく、家族で分け合う農民の食事」だと教わりました。どちらも誰かのために作る文化。共通するものを感じた頃から、分かち合う場を自分の手で作りたいという思いが芽生えてきたんです。
そんな折、長野の野田平キャンプ場で、サウナホリックこと森實敏彦さんに案内され、初めてテントサウナを体験しました。火を焚き、水を沸かし、蒸気をつくる。そのすべてが料理と同じ「熱の文化」で、体全体で火入れを感じる体験で…。そこからサウナにどっぷりハマり、「自分でもこんな場所をつくりたい」と思うようになりました。
 サウナストーブに据えられた鉄瓶と、和庭園の借景。茶室のように熱を味わう組紐KOBEのサウナ。
サウナストーブに据えられた鉄瓶と、和庭園の借景。茶室のように熱を味わう組紐KOBEのサウナ。
文化資源として価値ある庭園でととのいたい
── この美しい日本庭園と家屋には、どのように出会ったのですか。
ここはもともと私の妻の母親、義母の実家で、神戸唯一の醤油屋、池本醤油の分家の曾祖父が約120年前の大正初期に家を建て、産婦人科医だった祖父が増改築しながら、祖母が調度品を揃えたそうです。
 和洋折衷の美しい調度品の数々。邸宅が重ねてきた時間に思いを馳せるひととき。
和洋折衷の美しい調度品の数々。邸宅が重ねてきた時間に思いを馳せるひととき。
しかし法事でたまに使われるくらいで、長らく空き家として放置されていて。この家をどうするかは親族間で問題になっており、老人ホームやレストランなど転用のアイデアはあれど、全体で500坪ある土地をどうしていくか決めあぐねていたんです。
庭は日本庭園の巨匠・斉藤勝雄先生が手がけたもの。サンフランシスコ万博でも作庭した日本有数の造園師の作品ですから、時を経ても凛としていて、家と庭が呼吸するように調和していますよね。「この庭で外気浴をしたら、どれだけ気持ちいいだろう…」。それが発想の起点でした。
 100年以上経った今も当時の面影を色濃く残しつつ、美しいサウナ施設へと生まれ変わった。
100年以上経った今も当時の面影を色濃く残しつつ、美しいサウナ施設へと生まれ変わった。
── サウナとして運営をするにあたり、文化財としての維持やご家族との合意形成など、ハードルもあったのでは。
ここは神戸市指定景観資源「旧池本邸」として登録されており、市街化調整区域という土地柄、心証を悪くしないためきちんと許可を取る道を選びました。
2021年頃からサラリーマンを続けながら神戸市役所に通い、知らないことだらけの手続きに向き合って、許可が下りるまでに約2年。土日は掃除や片づけに費やし、100年分の荷をトラック2台分ほど捨て、使える状態に戻していきました。
手を入れ始めた頃は家族や親族も慎重な立場でしたが、少しずつ形にしていくうちに気持ちが通じ、今は応援してくれています。
料理に通ずる「ちょうどいい火入れ」の哲学サウナ
── サウナの設計士はどのような観点で選ばれましたか。
探したのは、庭と家のバランスを壊さず、ここに溶け込むサウナを作ってくれる人。候補は複数いましたが、アーティストリーの3D木工ディレクターの大西功起さんにサウナでお会いして、人柄、サウナへの考え方、作品、全てに好感を抱きました。
何がしたいのか、どんな未来を描きたいのか、私の思いを汲んだうえで「この庭の先」を見てくれて。前職が営業職だった私にとって、「相手の本当に必要なものを見極めて提案してくれる感性」が依頼の決め手となりました。
 アーティストリー大西さんが開発した、うつぶせ寝で休めるベッドCHILL DIVE。「小川の上に置くとせせらぎを眺められて最高なんです」と植月さん。
アーティストリー大西さんが開発した、うつぶせ寝で休めるベッドCHILL DIVE。「小川の上に置くとせせらぎを眺められて最高なんです」と植月さん。
── サウナに描かれた大きな円が印象的ですね。
庭の維持を学ぶために、亡き斉藤勝雄先生の唯一の弟子・枡野俊明さんにコンタクトを取り、横浜まで会いに行ったんです。枡野さんは僧侶で庭園デザイナー。毎日5分の椅子座禅と、心を無にして円相図を描くという、心を無にするアドバイスを受けました。
そしたら偶然にも大西さんから「植月さん、サウナの壁に円を描いてください」と言われたので、1ヵ月ひたすら心を無にして円を描く練習。円相図は禅において悟りや真理の象徴で、見た人の心を映し出すものでもあります。サウナに入ってから下書きなしで「えいやっ!」と描きました。
 黒に塗られたシックな壁面に、白い円相図が印象的。座面の下には玉砂利が敷き詰められており、茶室を思わせる。
黒に塗られたシックな壁面に、白い円相図が印象的。座面の下には玉砂利が敷き詰められており、茶室を思わせる。
── 温度は低めで心地良いですが、あっという間に汗が出て驚きました。
77℃という目安の温度はありますが、私が目指すサウナは数字で管理するものではありません。熱さを競うような我慢のサウナではなく、誰が入っても自然に深呼吸できる場でありたい。
アメリカンバーベキューのようにグリルで肉を焼くイメージで、芯まで温まる火入れを目指し、外気温や人数、湿度、室内の対流、お客様の好みなど、細かな要素の積み重ねでその日の最適解を探します。私にとってサウナとは、もてなしであり対話なので、お客様を見て「いまがちょうどいい」と感じてもらえる瞬間をつくりたいのです。
サウナ単体ではなく、この庭や食と合わせて初めて完成する体験。だからこそ効率ではなく、お客様ひとりひとりとしっかり向き合って、時間と手間を惜しまない運営を大切にしています。
── とても香りが良いサウナですよね。
サウナストーブはHARVIAをベースにした、石川の施工会社B.S.Aオリジナル仕様のもの。蔵から見つけた鉄瓶に自家栽培した季節のハーブを加えることで、蒸気に命を吹き込んでいます。
耕さず肥料も農薬も使わず、さまざまな植物を密生させて自然の生態系を生かす協生農法で育てたバジルは、香りが強くミネラルを豊かに含み、蒸したときに生命力のある香りを放つんです。
 もともと湿度づくりにはキッチンにあった銅鍋を使用していたが、思い描く蒸気にはならず、蔵から見つけた鉄瓶に切り替えたという。
もともと湿度づくりにはキッチンにあった銅鍋を使用していたが、思い描く蒸気にはならず、蔵から見つけた鉄瓶に切り替えたという。
ロウリュに使っているのは自生しているよもぎ。乾燥させたよもぎはお茶を淹れるように90℃弱の温度で煮出すと苦味が出ず、ほんのり甘みを帯びます。植物のエネルギーが宿った蒸気を浴びることで、体の内側まで優しくほどけていく感覚を得られるはず。
ロウリュには茶道具の柄杓を使い、その音と香りが、まるで点前の所作のように茶室のような空間をととのえてくれます。
水・庭・台所がつながる、ととのう循環
── とろけるような肌触りの水風呂は地下水ですか。
はい。敷地内に古くからある井戸を再生し、地下水を掛け流しで使っています。長く使われていなかったためポンプが壊れていましたが、付け直して水質検査も行いました。結果は軟水。近くの饅頭屋さんなんて、あんこづくりのためこの櫨谷の地に越してくるほど。水質が良い土地なんです。
一般家庭にあるような深さ7〜10メートルの浅井戸ですが、18℃前後の温度が一年を通して安定し、季節によって1〜2℃変わる程度。最初の1ヶ月ほどは少しニオイがありましたが、いまは無味無臭で量も増え、掛け流しができるほどになりました。
 水風呂には、屋外使用に強い亜鉛メッキ鋼板製のストックタンクを使用。頑丈で水温を保ちやすく、庭の景観にも馴染む佇まい。かけ水用の壺も備えている。
水風呂には、屋外使用に強い亜鉛メッキ鋼板製のストックタンクを使用。頑丈で水温を保ちやすく、庭の景観にも馴染む佇まい。かけ水用の壺も備えている。
── 庭にはインフィニティチェアだけでなく、小高くなっているところには寝転べるエリアや大岩などもあって、全て試してみたくなります。
外気浴は、この庭そのものが舞台です。板に身を預けて空を見上げると、鳥の声や虫の声、風がそよぐ音が耳に届き、自然と一体になるような感覚になります。計算され尽くした庭には静かな奥行きがあり、深く息を吸えば肩の力がすっと抜けていく。日常の喧噪から切り離され、深いととのいを感じられるはずです。
 すのこを置いただけだという「つきやまの板」。フルフラットではなく、少しだけ角度がついているのがポイント。木漏れ日が心地良い。
すのこを置いただけだという「つきやまの板」。フルフラットではなく、少しだけ角度がついているのがポイント。木漏れ日が心地良い。
庭を褒めてもらうことが多いのですが、私がもうひとつ気に入っているのが内気浴エリア。調湿効果のある漆喰壁に囲まれ、少し薄暗くて落ち着きますし、天井に取り付けたファンが優しく風を送ってくれます。とりわけ雨の日には雨音を聞きながらととのうのが格別。初めて訪れた方にもお勧めしたいスポットです。
 サウナの前室でもある内気浴エリア。「冷えすぎる時はここで休むのがお勧めです」と植月さん。
サウナの前室でもある内気浴エリア。「冷えすぎる時はここで休むのがお勧めです」と植月さん。
── 組紐KOBEでは宿泊もできるんですよね。
はい。宿泊していただくお客様には、ここに受け継がれてきたものをまるごと体験してほしいと思っています。蔵の中には、代々大切に使われてきたであろう一流料亭で使われるレベルの立派な食器がたくさん眠っていたので、朝ごはんなどに使っています。
 昔ながらのおくどさん(かまど)も現役で活用。炊飯器を使わず、手間暇かけて炊かれたごはんは格別。
昔ながらのおくどさん(かまど)も現役で活用。炊飯器を使わず、手間暇かけて炊かれたごはんは格別。
料理は昔ながらのやり方。おくどさん(かまど)を使い、庭の剪定で出た薪を燃やしてお米を炊く。スギやヒノキの薪で炊いたごはんは、お米本来の甘みや旨みがぎゅっと詰まって絶品です。添加物や旨味調味料を使わない昔の人が守ってきた美味しさを、ここで再現できたらと考えています。
さらに、もともとあったお風呂もすごく大切にしています。浴室や大窓の構造はそのままに、色を塗り替えただけのシンプルな仕上げですが、お風呂自体がめちゃくちゃ良くて。寒い冬にはお風呂で下茹でしてからサウナに入ると、芯まで温まるんです。
 「本当にお風呂が良いので、ぜひ入ってほしいんです!」と植月さん絶賛のお風呂。大窓のロールカーテンを開けると、庭が一望できる。
「本当にお風呂が良いので、ぜひ入ってほしいんです!」と植月さん絶賛のお風呂。大窓のロールカーテンを開けると、庭が一望できる。
泊まっていただくことで、サウナと庭と台所がひとつにつながる時間が生まれます。「古民家サウナでととのう休日」を、ぜひ体験してほしいですね。
文化を束ね、未来へ紡ぐ場所に
── サウナだけでなく宿泊までお一人で運営されると、オープン当初は大変なことも多かったのではないでしょうか。
宿泊のお客様と夜遅くまで一緒にお話しして、気がつけば睡眠時間が1時間なんてこともありました…(笑)。翌朝はお米を炊かなければいけないので、早起きしておくどさんに火を入れる。お客様にとっては一泊でも、私にとっては「準備から片付けまで丸一日」。でも喜んで帰っていただける姿を見ると、それだけで報われますね。
 水回りは築120年の家屋とは思えないほどきれいにリフォームされている。
水回りは築120年の家屋とは思えないほどきれいにリフォームされている。
── 「組紐KOBE」という名前にはどんな想いが込められているのでしょう。
この家の和室にはもともと組紐が飾られていて、調べていくうちに心を惹かれるようになりました。一本の糸では弱いですが、何本もの糸を重ね、束ねることで強さと美しさが生まれますよね。それは、ここで紡ぎたい文化に重なると思ったんです。
サウナ、日本庭園、おくどさん、バーベキュー、パエリア…。一見バラバラに見える要素ですが、どれも長い歴史の中で大切にされてきた文化です。それらの文化を束ね、次の世代につないでいきたい。そんな願いを込めて「組紐」と名づけました。
 施設名となった、床の間の柱に飾られた組紐。いつ誰がどんな願いを込めてこれを飾ったのかはわからないという。
施設名となった、床の間の柱に飾られた組紐。いつ誰がどんな願いを込めてこれを飾ったのかはわからないという。
言葉では説明しきれないものを、体験として丸ごと持って帰ってほしいんです。「あの庭で外気浴したら気持ちよかったな」「おくどさんのご飯が忘れられない…」。そういったひとつひとつの感覚が、紡がれつながっていく。その積み重ねが、この場所の存在意義なんじゃないかと思っています。
── 組紐KOBEの展望をお聞かせください。
目指しているのは、「サウナ好きが大切な人を初めてサウナに連れて行くときに選びたい場所」です。サウナに慣れた人だけでなく、サウナに苦手意識がある人や、まだ一度も入ったことがない人に、その心地よさを知ってもらいたい。ここでの体験が、その人のサウナの入口になれたら嬉しくて。
実際「他では暑すぎて入れられなかったけど、ここなら大丈夫だった」という声もあって、そんな言葉たちに支えられています。
 植月さんの畑。協生農法により、バジルと茄子が雑草と共に力強く育っている。料理やロウリュで、その生命力を感じられるはず。
植月さんの畑。協生農法により、バジルと茄子が雑草と共に力強く育っている。料理やロウリュで、その生命力を感じられるはず。
この庭と家が重ねてきた歴史のぬくもりに包まれながら、様々な文化が紡がれる体験を通して、誰かの健康や前向きな変化のきっかけになるような場所にしたい。ここから始まるサウナとの出会いが、人生の景色まで少し変えてくれる…そんな場になれば最高ですよね。
記事の感想をいただけると
次回の記事の励みになります!

 相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ
相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ

 相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ
相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ

 相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ
相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ

 相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ
相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ

 相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ
相沢 あい
さんに37
ギフトントゥ
記事を書いた人

サウナ大好きクリエイティブディレクター。サウナイキタイでは、アドベントカレンダーやサウナイキタイマガジンの編集を一部担当。
普段はコピーや構成台本を書いたり、グッズのデザインをしたり、編集をしたり、MCをしたり、過去にはテレビ朝日『お願い!ランキング』のレギュラーレポーターだったりと、「結局何やってる人なんだろう」と思われがち。著書に『ズボラ美容』。