【閉店】湯あそびひろば 6・3の湯
温浴施設 - 愛知県 西尾市
温浴施設 - 愛知県 西尾市
ちょいと遅くなってしまったが墓参り。ふと気がついたけど、これまでお参り中でもいつでも頭の中で勝手に思考プログラムが動作している感じだったが、ここのところ思考の一時的なシャットダウンが出来るようになった気がする。余白を作るのは大事だと思ってたから、感覚のレンジが拡張したような実感ってのは嬉しいね。多分サウナ習慣のおかげが大きいです。
さて今夜も元気に6・3へ、盆休み3連チャン。2セット目の20:30アウフグース、残念ながら最上段は座れなかったけど今回も分厚い熱波でとても良かった。流れ良く今夜も6セット、去年から比べると随分こなせるようになりました。
-----
【読書まとめ・風呂とエクスタシー19】
世界風呂史の各論、興味深いサウナ・バーニャの起源について。総論でも既に述べたように、フィンランドのサウナと、ロシアのバニアは基本的に同じ構造であるが、サウナは電熱器で石を焼いたり、熱風を送る設備や熱輻射盤を併用するといった技術革新を行ったことが、サウナを世界的に普及させたひとつの理由である。
歴史を辿ると、まず近代的なサウナのもとになった形は、地上の小屋にかまどを設け、かまどに煙突がついたタイプ。一つ古いサウナには煙突がなく、小屋に煙が充満するが、小屋自体も熱せられる。この場合、火が燃え尽きてから、焼石に水をかけ、湿気と温度を上げるとともにその蒸気で煙を追い出してから入る。さらに古いタイプのサウナを探すと、半地下の小屋を用いたサウナがあり、これはロシアのバニアでも同様で、記録に残っているサウナを遡る道はここまでである。
ところが、ロシアには興味を引く古い記録があり、それはロシア南部・東部において、パン焼き窯を熱気浴にも利用したもので、文字通りまさに窯風呂であり、朝鮮の「汗蒸」や日本の窯風呂と起源を同じくするものであると考えられる。
なお、フィン族はウラル系の民族で、ロシアはスラブ系。多くのスラブ系の民族は風呂を持っていなかったことを考慮すると、サウナのような風呂の起源がスラブ系とは考えられず、やはりウラル系かあるいはシベリアのパレオシベリア系の民族から伝えられたと考えるが妥当と本項ではまとめている。
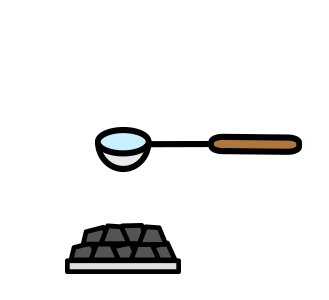
今、泥酔中で論点からずれていたらすみません。①オンorオフが大事、②自分の事例ですが、サ室で、ひたすら汗の水滴数を数えることに集中し他事を考えない、などを想起しました。その応用でレンジ拡張までは至っていませんが汗。
コメントすることができます
すでに会員の方はこちら