【閉店】湯あそびひろば 6・3の湯
温浴施設 - 愛知県 西尾市
温浴施設 - 愛知県 西尾市
今日はお盆の親戚寄り合いで木曽路のしゃぶしゃぶ、以前ニュースで見た高級肉がコロナで安値、というのに関係してるか分からんけど今日の肉は美味かった。普段は行かないけど、年イチくらい寄り合いで頂くのがちょうど良いね。
6・3の350サ活目だ、てやんでい。いつの間にか愛知県でもかなりサ活数上位に食い込んできてて、評価はどうあれ最後に6・3を味わった人が増えてなんか嬉しい。サ室・水風呂・外気浴、スキがないよね。コツコツやるが信条だけど、6・3のサウナは一回一回のコツが楽しくて、結局時間が合えば40分掛けて来ちゃう。今夜は良い感じの流れがキて珍しく連続6セット。アウフグースか外気浴が良いときか、たまに来るこの良い流れに乗るのは何かがキーになってる気がするけど、求めちゃうと離れる類のものだと思うんであんま考えないようにしてる。良いサウナでした。
-----
【読書まとめ・風呂とエクスタシー18】
世界風呂史の各論、日本の熱湯浴についての章をまとめてみよう。世界を見渡して日本ほど熱湯浴が普及しているところはない。その元になったのは、仏教寺院の風呂である。日本には仏教とともに取り湯式の風呂と、湯釜型の蒸気浴が伝わり(焼石型蒸気浴は三重・伊勢に見られたが定着せず)、この中から2つの公衆風呂が平安時代に現れた。取り湯式の「湯屋」、湯釜型蒸気浴の「風呂屋」である。
「風呂屋」からは「ざくろ口」や「戸棚風呂」のように、熱湯を少し入れた浴室で蒸気浴をするような、熱湯浴と蒸気浴の中間的な風呂が現れ、これらは世界に類を見ない。また一方、「湯屋」ももともとは場を汚さぬよう、かけ湯のみで浴槽には浸からなかったのだが、いつからかは不明ながら、浴槽に入る熱湯浴が派生し、風呂桶を下から焚くタイプの風呂「 据風呂(すいふろ)」が現れた。かの如く蒸気浴の影響で熱い湯となり、日本の熱湯浴が成立した。

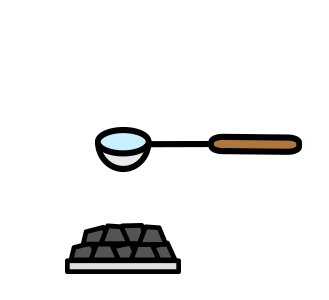
現代の風呂文化「
コメントすることができます
すでに会員の方はこちら