【閉店】湯あそびひろば 6・3の湯
温浴施設 - 愛知県 西尾市
温浴施設 - 愛知県 西尾市
6・3に行く途中、Youtuberの東海オンエアの聖地として一躍有名になった横浜家系ラーメン「まんぷく家」の横を通るんだけど、ここんとこその行列たるや尋常じゃない。元々はちょくちょく食べてて中々美味い店なんだが、自分にとっては1時間以上も並ぶほどではないんでそれからは行ってない。それで良いじゃん!
今夜の6・3もまんぷく家ほどでは無いけどサ室が盛況で、20:30アウフグースで珍しく最上段が埋まってた。こんな経験は2回目くらいで、悲しいやら嬉しいやら。かなり熱かったけどみんな最後まで受け切ってて良かった。施設イチ押しパインジュースの宣伝で2人体制、うちわとタオルが唸ったあとは恍惚の水風呂と外気浴。やっぱりこのバランスがたまらんです。早めに上がろうかと思ってたけど、コンディション良かったんで結局5セット!うきうきぶろ〆。
-----
【読書まとめ・風呂とエクスタシー13】
日本の風呂史-2。まずは仏教伝来の風呂の系譜。最古の資料、奈良時代の大安寺、法隆寺の資財帳(747年)を見るに、湯浴と蒸気浴の2説が考えられるが、本書では蒸気浴メインと考えている。それ以降の仏教寺院の殆どに、釜で湯を沸かし、蒸気を温室に送り込む形式での蒸気浴が見られた。そして、仏教寺院の蒸気浴は一般に広まり、佐渡の「おろげ」、三重の鈴鹿・伊賀の「ふごふご」、近江八幡の「飛び込み風呂」、滋賀湖北〜北陸の「むぎぶろ」等、いずれも蒸気浴と湯浴の中間形態を示している。
秀吉の朝鮮出兵の頃から桶を使った個人用の風呂が登場し、初めは蒸気浴、後に五右衛門風呂が関西で広まり、蒸気浴から熱湯浴への変化がここで起こる。日本の風呂系譜の最後は、宮中や寺院の風呂形態「取り湯」であるが、長くなるのでまた次回!

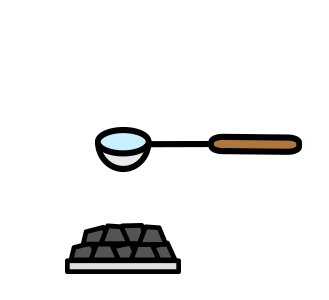
コメントすることができます
すでに会員の方はこちら