サウナ&カプセルホテルレインボー本八幡店
カプセルホテル - 千葉県 市川市
カプセルホテル - 千葉県 市川市
その金曜日の夜、小雨が街を濡らしていた。五月下旬の雨は、まるで季節が自分の居場所を探しあぐねているみたいに、優柔不断に空から落ちてくる。一週間という名の長いトンネルを抜けた僕は、疲労という重いコートを肩にかけたまま、本八幡の駅前に立っていた。仕事の残響が頭の中でエコーのように響き続けている。それは消えかけのラジオの雑音のようで、どうしても完全に消すことができない種類の音だった。
本八幡レインボーの看板が雨に濡れて光っていた。駅から一分という距離は、現実と非現実を繋ぐ短い橋のようだった。僕はまるで迷子になった子供のように、いや、正確に言うなら自分の居場所を見つけようとする37歳の男のように、その扉を押し開けた。初めての場所に足を踏み入れるときの、あの微妙な緊張感が胸の奥にあった。
更衣室で服を脱ぎながら、僕は一週間分の重力から解放されていくのを感じていた。イオンウォーターを買い忘れたことに気づいたが、それはもうどうでもいいことのように思えた。ジャグジー風呂の泡が肌を包むとき、僕の頭の中の雑音は少しずつ静かになっていく。
瞑想サウナの扉を開けた瞬間、80度の熱気と香りが僕を迎えた。暗闇の中で、僕は自分という存在の輪郭を確認するように座っていた。香りは何だろう、ヒノキのような、それとも別の何かのような。それは記憶の奥底に眠っている何かを呼び覚ますような匂いだった。目を閉じると、仕事のことも、明日のことも、すべてが遠い場所の出来事のように感じられた。
昭和ストロングスタイルという名前からして只者ではないサウナ室に足を踏み入れたとき、120度の熱気は僕の皮膚を通り抜けて魂まで焼こうとしているみたいだった。最上段に座った僕は、まるで太陽の表面にいるような錯覚に陥った。肌を刺す熱さは、現実と非現実の境界線を曖昧にする。4分という時間が永遠のように感じられて、僕はひとつ下の段へと逃げ込んだ。それは敗北ではなく、適切な距離を見つける行為だった。黙浴という静寂の中で、僕は自分の呼吸音だけを聞いていた。
16度の水風呂は、焼かれた魂を優しく受け止めてくれる母親の腕のようだった。柔らかい水質が僕の疲れた体を包み込む。カルキ臭さがないというのは、こんなにも心地よいものなのか。
休憩室に足を向けたとき、予想を遥かに超えた広さが目の前に広がった。それは小さな発見という名の宝物のようだった。想像していた4倍、いや5倍もの広さがそこにはあって、僕は小さな驚きとともにゆったりとした時間の流れを感じていた。
帰り道、日高屋のカウンターに座った僕は、ザーサイとビールを注文した。塩っぱいザーサイの味が、今夜の体験に句読点を打ってくれた。小雨はまだ降り続けていたが
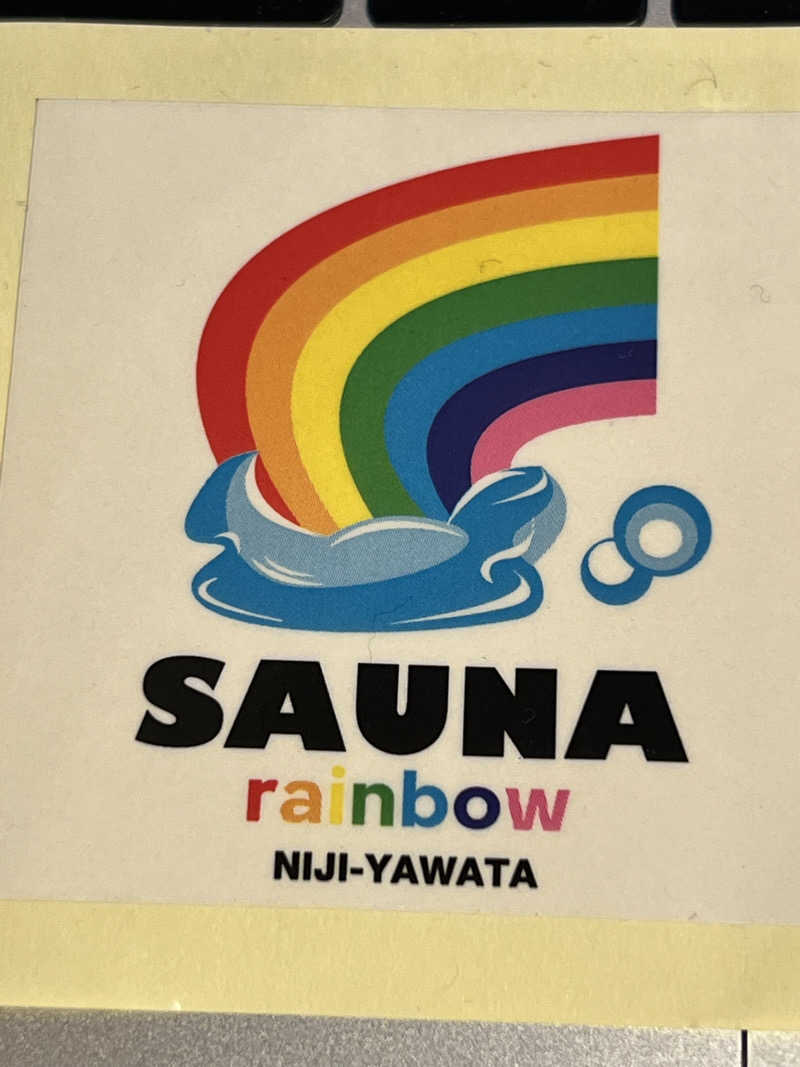
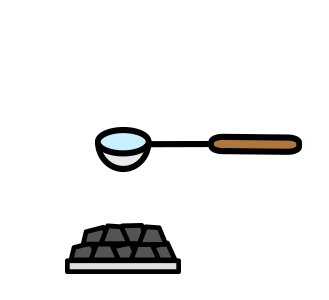
コメントすることができます
すでに会員の方はこちら